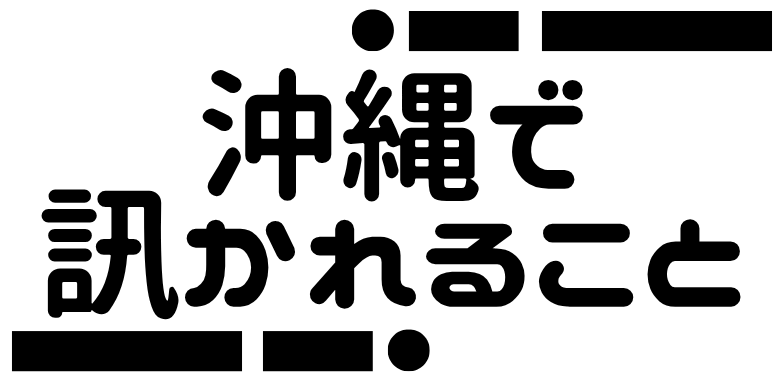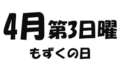沖縄でも地震や津波は起きます。たとえば、2024年、沖縄県で震度1以上の地震が57回計測されました(気象庁「震度データベース検索」)。また気象庁の「潮汐・海面水位に関する診断表、データ」では2024年4月3日の沖縄県与那国島において最大27cmの津波が記録されています。
とりわけ沖縄県の津波については、「明和の大津波」が有名です。18世紀に編纂された歴史書『球陽』にも記述されているそうです。国立大学法人琉球大学の島嶼防災研究センターによれば、1771年4月24日の午前8時頃、八重山諸島沖で地震が発生し、遡上高85メートルの津波が八重山諸島や宮古諸島に達し、11,800人以上の人々が亡くなったと言われています。
沖縄県において震度1以上は985回(2014年~2024年の累計)
ここからはデータが充実している地震に注目したいと思います。2024年は沖縄で震度1以上の地震が57回ということですが、2014年から2024年の10年間ではどのような様子だったのでしょうか。この10年間で沖縄県で計測された震度1以上の地震は985回(気象庁「震度データベース検索」)でした。この回数を10で割ると98.5となります。「沖縄県では震度1以上の地震が毎年およそ100回は計測された」と言えそうです。
さて、この2024年の「57回」、ここ10年で「985回」という沖縄県における震度1以上の地震回数は他県と比べて多いのでしょうか?それとも少ないのでしょうか?
沖縄の地震、九州・沖縄地方の中では「やや少ない」ほうだけど…
気象庁「震度データベース検索」を使って、2024年の九州・沖縄地方を集計してみました。この地域における震度1以上の地震は合計590回、平均約73回、中央値59回でした。最多は鹿児島県の212回、最小は福岡県の19回。2024年、沖縄県は57回でしたので、「鹿児島県の1/4くらいの回数で、九州・沖縄地方の中央値と比べれば、やや少ない頻度で地震が発生した」と言えそうです。
続いて、九州・沖縄地方の2014年から2024年までの10年間で比較するとどうなるでしょう。震度1以上の地震については、気象庁「震度データベース検索」では鹿児島県、熊本県、宮崎県、大分県の結果が千件を超えるため表示されませんでした(そのようなシステム仕様のようです)。その代わりに、震度3以上に限定して集計しました。震度3以上は合計60回、平均7.5回、中央値6.5回でした。最多は鹿児島県の16回、最小は福岡県と佐賀県の2回。この10年間の沖縄県の頻度は5回でしたので、「鹿児島県の1/3くらいの回数で、九州・沖縄地方の平均値や中央値と比べると、やや少ない頻度で地震が発生した」と言えそうです。
2020年の沖縄の地震、全国の平均や中央値よりは「多いほう」
日本全国における沖縄県の地震頻度について比べてみましょう。気象庁の「令和2年(2020年)の都道府県別の震度観測回数表」には2020年の全国の地震回数が整理されています。この資料によれば、2020年、全国において震度1以上は1714回観測されたそうです。全国の平均約70回、中央値40回でした。最多は261回(長野県)、最小は7回(香川県)。この年の沖縄県は震度1以上が99回でしたので、「2020年の震度1以上で比較すると、沖縄県は全国平均や中央値よりも地震が多い」と言えます。
同じ資料において震度3以上に限定して集計すると、2020年の全国の地震回数は164回、平均約6.6回、中央値2でした。全国で最多は茨城県の35回、最小は京都府や長崎県などの0回。この年の沖縄県の回数は7回でしたから、「2020年の震度3以上に限定しても、沖縄県は全国平均や中央値よりも地震が多い」と言えます。
要約すると、沖縄県の地震は九州・沖縄地方の中では「やや少ない」です。おそらく、鹿児島県、熊本県、宮崎県、大分県における地震の回数が相当多いからだと思われます。また、2020年の全国の比較に限って言えば、沖縄県の地震は全国平均や中央値よりも「多い」です。
沖縄の地震は海溝や内陸の活断層で発生
石垣島気象台や海上保安庁の海域火山データベースによれば、沖縄県には西表島北北東海底火山があります。この火山は1924年10月31日に噴火し、多量の軽石が日本各地に漂着したそうです。しかしながら、地震調査研究推進本部事務局によれば、沖縄県の地震は日向灘、南西諸島海溝周辺、南海トラフといった海溝で発生するものと、宮古島断層帯(内陸の活断層)で発生するものに分類されるそうです。記録に残されている沖縄の地震に関しては「火山が原因とするよりも、海溝や内陸の活断層で発生した」と説明するのが正しそうです。