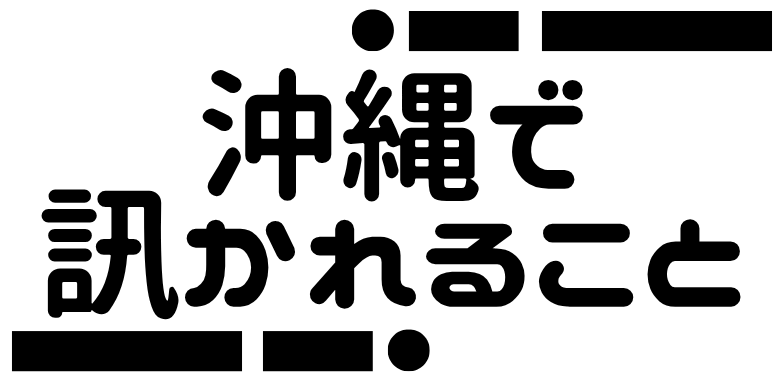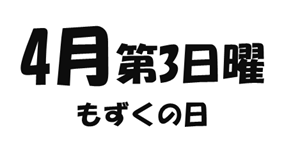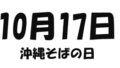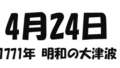商品化が目立つモズクと海ブドウ
沖縄の観光地に行くと必ず目に入る商品がモズクと海ブドウです。海ブドウはクビレズタとも呼ばれます。いずれも色は緑系ですが、形状が異なります。モズクは細長い糸状、海ブドウは果物のぶどうのような房(ふさ)に似ています。
商品としては株式会社沖縄海星物産の「天然太もずく」シリーズや久米島海洋深層水開発株式会社の「球美(くみ)の海ぶどう」がよく知られています。
またモズクや海ブドウの関連商品も充実しています。例えば、有限会社セイワ食品の「もずくうどん」、株式会社海宝の「沖縄もずくと芽かぶのとろ〜りスープ」、株式会社もずキムの「もずキム」、株式会社日本バイオテックの「生海ぶどうソフトクリーム」などがあります。
この記事では沖縄産のモズク、海ブドウ、そしてアーサーの産業統計上の特徴に注目したいと思います。
モズクや海ブドウなどの海藻類と沖縄の健康や長寿との関係については他の専門書や報告書を参考にしてください。
沖縄産モズク、日本市場を独占
日本で採れるモズク類のほぼ100%が沖縄県産です。例えば、2023年、沖縄県では約2万トンのモズク類を生産し、日本のモズク類シェアの99%以上を占めていました(農林水産省「海面漁業生産統計調査」)。農林水産省による養殖魚種別収獲量累年統計のデータを基に、1995年から2020年の25年間で平均してみると、毎年15,900トンくらいは収穫したことになります。
モズク類の生産量だけでなく、その産出金額も調べてみたところ、2023年の沖縄県は25億3,100万円(農林水産省「都道府県別統計表(海面漁業・養殖業産出額)(令和5年)」)でした。この年の日本全国のもずく類産出額は25億6,200万円(農林水産省「漁業産出額 魚種別産出額累年統計 海面養殖業」)でしたから、金額においても沖縄産モズクが日本産のモズクのほぼ100%占めていることになります。
つまり、生産量・産出金額の両方において、沖縄産のモズク類は日本全国を独占しています。
知名度の海ブドウ(クビレズタ)
モズクと並んで存在感のある海ブドウ(クビレズタ)についても調べてみましたが、インターネットに公開されている記録がなかなか見つかりませんでした。海ブドウは「その他の海藻類」として扱わられているからかもしれません。
ようやく見つかった資料が沖縄県サイトで公開されている「Ⅴ沖縄県の水産業」でした。2008年から2020年までの海ブドウ生産量と産出額が掲載されています。この12年間に限れば、年間生産量は平均で332トン、最も多い年では462トン(2014年)、最も少ない年では226トン(2009年)でした。
海ブドウの産出金額でみると、2008年から2020年までの年平均は約8億円、最多は12億1,100万円(2014年)、最小は6億2,800万円(2010年)でした。
沖縄の海ブドウはモズクにも優るとも劣らない存在感がありますが、その生産量・産出額の規模はモズクよりも小さいことがわかりました。
てんぷらで重宝されるアーサー(ヒトエグサ)
モズク、海ブドウ(クビレズタ)と来れば、「アーサー」も気になってきます。アーサーも沖縄の家庭料理でよく使われ、てんぷらやお吸い物の具材として見かける頻度は高めです。ちなみにアーサーはヒトエグサとも呼ばれます。
幸い、海ブドウで参考にした資料「Ⅴ沖縄県の水産業」には、沖縄のアーサーの生産量と産出額も載っていました。2008年から2021年までの期間、沖縄産アーサーの年間生産量は平均で約68トンでした。最も多い2018年で105トン、最も少ない2008年で46トンです。2008年から2022年の年産出額は平均で約9,500万円、最も多い年は2018年の1億3,400万円、最も少ない年は2020年の7,100万円とのことです。
沖縄県内におけるアーサーの生産量と産出金額は海ブドウよりも小さいということがわかりました。
市場規模はモズクが圧倒的に大きい
以上、沖縄で有名なモズク、海ブドウ、そしてアーサーについて調べてきました。どれも存在感は同じですが、沖縄におけるモズク、海ブドウ、アーサーの生産量・産出額について大小記号を使って並べると、
アーサー < 海ブドウ < モズク
という順番になります。平均した年間生産量に焦点を当てれば、モズク15,900トン、海ブドウ332トン、アーサー68トンです。アーサーの年間生産量を1とすると、モズクはアーサーの約233倍、海ブドウはアーサーの5倍弱の生産規模になります。しかも沖縄産モズクは日本市場も独占しています。
昆布(こんぶ)も有名ですよね?
ここまで読んでいただいて「沖縄と言えば昆布(こんぶ)も有名ですよね?」と思われた方々もいらっしゃるかもしれません。
昆布も沖縄料理でよく使われる食材ですが、これは沖縄県外から輸入しているそうです。2023年の農林水産省による「2大海区都道府県振興局別統計 (2)魚種別漁獲量」にも、沖縄の「こんぶ類」はデータがありません。なお、この資料によれば日本の昆布はほぼ100%が北海道と青森県で獲られています。
「でも、昆布の消費量は沖縄県が全国1位ですよね?」と思われた方々もいらっしゃるかもしれません。都道府県ごとの昆布消費量の資料が見当たらなかったので断言はできないのですが、現在では他の都道府県が昆布消費量の上位を占めていると思われます。
その根拠となるのは、県庁所在市と政令指定都市における昆布消費傾向です。総務省統計局による「家計調査(二人以上の世帯) 品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市(※)ランキング(2022年(令和4年)~2024年(令和6年)平均」という資料を見てみましょう。
この家計調査によれば、2022年から2024年において昆布の消費額は富山県富山市、消費数量は岩手県盛岡市が1位でした。一方、沖縄県庁の置かれている那覇市は14位という記録でした。沖縄県の「統計トピックス ◇こんぶ大国首位返上!?」という資料にも、平成元年(1989年)以降は那覇市が1位ではないと書かれています。2009年(平成21年)から2024年(平成6年)までの総務省統計局の家計調査(二人以上の世帯)を基にした順位表も調べてみましたが、ここにおいても那覇市は11位から32位の間に位置していました。
結論としては、昆布は沖縄では獲れませんし、昆布消費量や消費額においても沖縄県は日本1位ではななさそう、ということになります。